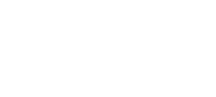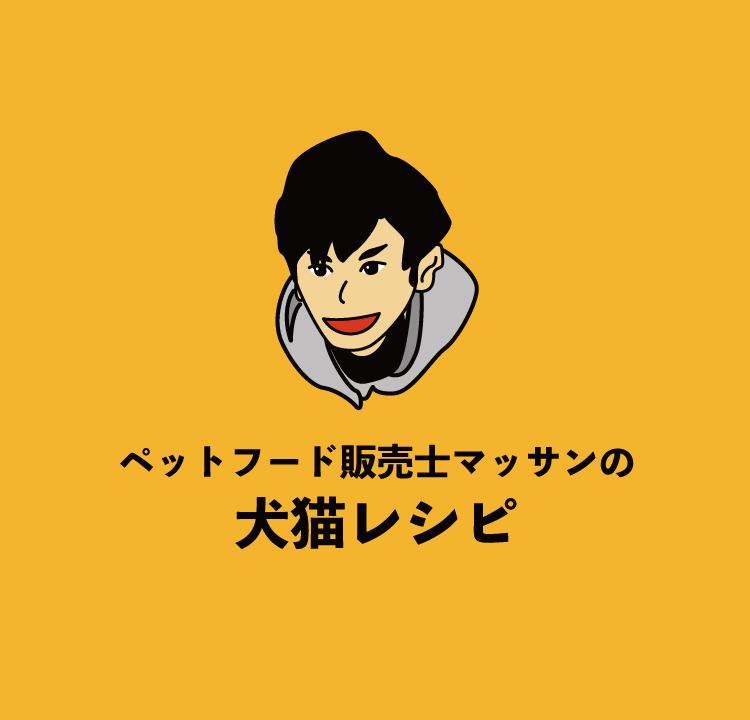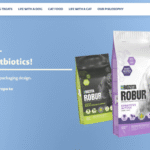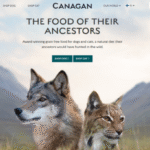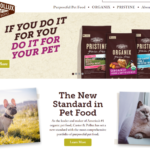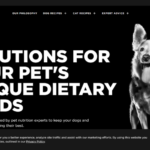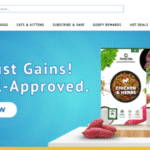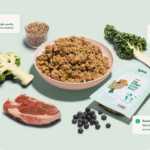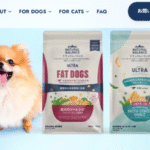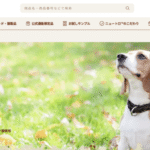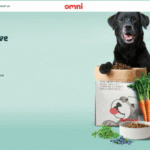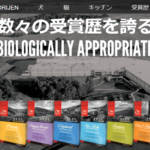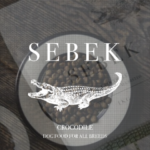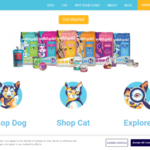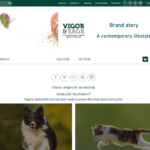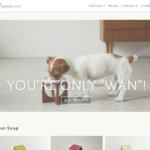吠え続ける、噛む、家具を壊す、拾い食い、トイレを失敗する…こうした行動は「問題行動」と呼ばれ、悩む飼い主さんも多いのではないでしょうか。
これらの問題行動をするのには必ず理由があり、犬なりのサインであることがほとんどです。
この記事では代表的な犬の問題行動を一覧でわかりやすく整理し、それぞれの特徴や原因について、また問題行動を放置するとどうなるのかについても解説します。
問題行動を正しく理解することで、愛犬との信頼関係を深め、より良い暮らしを築くための第一歩にしていきましょう。
問題行動とは
犬の問題行動とは、
- 飼い主にとって望ましくない行動
- 人間社会で支障となる行動
のことを指します。
犬にとっては自然な行動であっても、人間の生活環境ではトラブルやストレスの原因になるため「問題」として捉えられることが多くあります。
攻撃行動、過剰な吠え、破壊行動、排泄の問題など多岐にわたり、それぞれに原因・背景・対処法が異なります。これらの行動は犬自身が「わざと」行っているわけではないケースも多くあります。
「しつけが悪いから問題行動を起こす」と決めつけてしまうのは危険です。無理に押さえつけるよりも、「なぜその行動が出るのか」を理解し、根本原因にアプローチすることが重要です。
犬の問題行動一覧と特徴
ここでは、代表的な犬の問題行動12種類とその概要を解説します。
それぞれの関連記事から、その問題行動の特徴や原因、対策などの詳細をご覧いただけます。
①無駄吠え、過剰な吠え
犬の無駄吠えが多かったり過剰に吠えるのは、要求を伝えたい、不安を感じている、警戒している、興奮しているなどの理由によるものです。
要求吠えではおもちゃやおやつをねだって吠え続けたり、警戒吠えではインターホンの音や通行人に向かって吠えることが多く見られます。また高齢や認知症によることも考えられます。
まずは吠えの原因を見極め、環境改善や適切なトレーニングで対策を行うことが重要です。
②人や犬を噛む、攻撃する
犬が他の犬や人、飼い主さんに対して噛む、唸る、飛びかかるといった攻撃的な行動をとる背景には、恐怖や防衛本能、過剰なストレス、痛みが隠れていることがあります。
例えば、体を触ろうとしたときに唸ったり、散歩中に見知らぬ犬や人に対して吠えたり飛びかかろうとする行動が挙げられます。
③家具を噛む、破壊する
家具を噛んだり、クッションを裂いたり、壁や床を引っ掻くなどの破壊行動は、主に退屈、不安、運動不足、ストレス過剰から引き起こされます。
室内のものを無差別に壊す、カーペットを掘り返すといった行動が見られる場合は、エネルギー発散や心のケアが必要です。
④分離不安
飼い主と離れることに強い不安を感じる犬は、留守番中に吠え続けたり、家具を壊したり、粗相をしてしまうことがあります。これを分離不安といいます。
出かける準備を始めるだけで落ち着きがなくなったり、ドアや窓を引っ掻いて脱出しようとする行動も典型的です。
深刻な不安障害であるため、早めの対策が大切です。
⑤トイレの失敗
決められた場所以外で排泄してしまう行動には、トイレトレーニングの未完成だけでなく、ストレスや体調不良、マーキング本能などさまざまな原因があります。
普段はできていたのに急に失敗する、特定の場所にマーキングするようにおしっこをかける、などの行動が目立つ場合は原因を見極めたうえで対応する必要があります。
⑥社会化不足
子犬期に十分な社会化を経験していない犬は、大人になってから知らない人や犬、物音、見慣れないものに対して強い恐怖や警戒心を抱きやすくなります。
突然吠えたり、後ずさりしながら唸る、あるいは恐怖から攻撃に出るケースもあります。
無理に慣れさせようとせず、段階的に安心できる経験を積み重ねていくことが大切です。
⑦異物の誤食・拾い食い
散歩中に石やタバコの吸い殻などを拾い食いしたり、家の中で靴下やプラスチック片を噛んで飲み込もうとする異食行動は、好奇心、ストレス、栄養不足などが背景にあります。
時には、目を離したすきに台所のごみ箱を漁るなどの行動に発展することもあり、健康被害のリスクも高いため早めの対処が必要です。
⑧食糞
犬が自分や他の動物の糞を食べる行為を「食糞」といいます。子犬期に見られることが多く、母犬の影響や好奇心、栄養不足、ストレス、退屈などが原因です。
叱ることで逆に隠れて行うようになることもあるため、糞の処理を早めに行い、運動や遊びを増やして環境を整えることが有効です。
⑨マーキング
マーキングとは尿で縄張りを主張する行動で、とくに未去勢のオス犬に多く見られます。新しい環境や来客時、他犬の匂いなどが刺激となり、室内でもマーキングすることがあります。
叱るだけでは改善しにくく、去勢手術や環境調整、適切なトレーニングでの対応が重要です。
⑩異常な興奮
犬が落ち着きを欠き、異常なほど興奮しやすくなるのは、運動不足や刺激耐性の低さが影響しています。
飼い主さんが制御できないほど興奮して跳びつく、散歩中にリードを引っ張り続ける、常にウロウロして落ち着かないなどの行動が見られます。
エネルギー発散とともに、落ち着きを教えるトレーニングが必要です。
⑪マウンティング
犬が他の犬や人、クッションなどに対してマウンティングする行動は、性的本能やストレス発散、優位性アピールなどの理由で起こります。とくに興奮したときや、緊張した場面で急にマウンティングする場合もあります。
無理に叱るのではなく状況を見極めながら対応することが求められます。
⑫過剰なグルーミング
自分の体を過剰に舐めたり噛んだりする行動は、ストレスや退屈、皮膚のかゆみ、アレルギー、痛みなどが原因で起こります。舐めすぎると皮膚炎や脱毛を引き起こすこともあり、心因性の問題が関与する場合もあります。
犬の問題行動の原因とは?
犬が問題行動を起こす原因はそれぞれ異なりますが、主に下記が考えられます。
- 本能や習性
- 社会化不足
- ストレスや不安
- 退屈・エネルギー過多
- 飼い主による無意識の強化
- 不適切なトレーニングやしつけ
- 病気や痛み、体調不良
- 加齢による認知機能の低下
このように、犬が問題行動を起こすのは単なるわがままではないことが分かります。
原因を正しく見極めることが、問題行動の改善には欠かせません。
問題行動を放置するとどうなる?

問題行動は時間とともに自然に治るものではありません。
問題行動は放置すればするほど犬にも飼い主さんにも大きなダメージが積み重なり、回復が難しくなります。
早めに原因を見極め、適切な対策をとることで、犬も飼い主さんもより安心できる生活を取り戻すことができます。
①犬に負担がかかり続ける
問題行動を放置すると、犬自身に大きな心身的ストレスがかかり続けます。
吠え続けたり、攻撃行動を繰り返すことは単なる癖ではなく、犬が何らかの不安や葛藤を抱えているサインです。その状態を無視してしまうと、慢性的なストレスによって体調を崩したり、免疫力が低下するリスクも高まります。
また、常に不安や緊張を感じていると心のバランスが崩れ、より攻撃的になったり、抑うつ状態に陥ることもあります。
犬にとって健やかな生活を送るためには、心と体の両方のケアが欠かせません。問題行動の背景にある負担に早く気づき、適切なサポートをしてあげることが大切です。
②飼い主との信頼関係が悪化
問題行動が続くことで、飼い主さんと犬との信頼関係にも悪影響が及びます。
吠える、噛む、トイレを失敗するなどの行動にイライラしてしまい、犬を叱る回数が増えると、犬は飼い主さんに対して不安や警戒心を抱くようになります。
信頼関係は一度崩れると、修復には時間と努力が必要です。問題行動を単なる「困った行動」として叱るのではなく、犬からのサインだと受け止めて寄り添う姿勢を持つことが、信頼関係を守るためには欠かせません。
③近隣トラブルへ発展
犬の問題行動を放置すると、近隣とのトラブルに発展するリスクも高まります。
とくに吠えすぎや夜間の騒音、庭や散歩中のマーキング行動などは、周囲の人々に迷惑をかけてしまうケースが多く見られます。苦情が寄せられることで飼い主さん自身の精神的負担も大きくなり、最悪の場合、住環境を変えざるを得ない事態に発展することもあります。
犬と暮らすうえで、周囲との良好な関係を保つことも重要なマナーのひとつです。犬の行動をきちんと管理し、問題行動が起こった場合は早めに対処することで、トラブルを未然に防ぐことができます。
④問題行動が固定化・悪化する
問題行動は繰り返すほど犬にとって習慣化していきます。
問題行動をすることで飼い主が構ってくれた・おやつをくれたなどの成功体験が積み重なると、犬にとってその行動が「正解」として定着してしまいます。
時間が経つほど修正が難しくなり、改善にはより多くの時間と専門的な介入が必要になる場合があります。
⑤飼い主の生活の質が低下
犬の問題行動によるストレスで、飼い主さん自身が精神的に追い詰められるケースも少なくありません。
「どうして言うことを聞いてくれないんだろう」と悩んだり、夜吠えで睡眠不足になったり、外出や旅行ができなくなるなど、生活の自由度が大きく制限されることもあります。
愛犬との生活が「楽しみ」ではなく「負担」になってしまうのは、本来望ましい関係ではありません。
⑥外出先や公共の場でのトラブル
社会化が不十分だったり、他犬への攻撃性があるまま放置していると、ドッグランや公園、動物病院など公共の場で他の犬や人に危害を加えるリスクが高まります。
最悪の場合は事故や損害賠償問題に発展する可能性もあり、飼い主さんの責任が問われる事態にもなりかねません。
まとめ
犬の問題行動には必ず原因があり、犬なりの理由があります。飼い主さんがそのサインを正しく受け止め、理解し、対策することが問題行動の解決への一歩です。
犬の問題行動に関して飼い主さん自身で対処しきれないと感じた場合は、早めに獣医師やドッグトレーナーなど専門家に相談しましょう。独自の判断で対応を続けると問題行動が悪化したり、犬との関係性にさらに悪影響を与えるリスクもあります。
それぞれの問題行動についての詳しい対策は、リンク先の記事からさらに深掘りしてご覧ください。