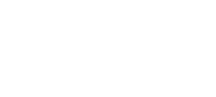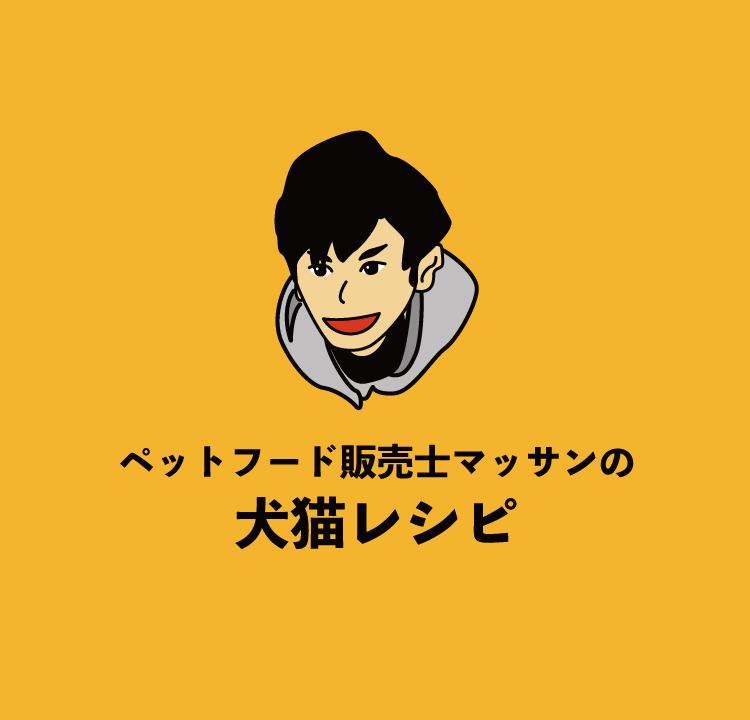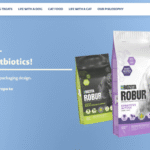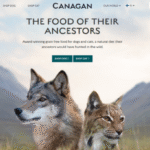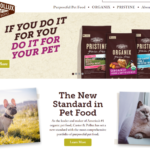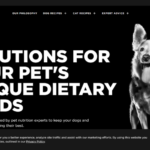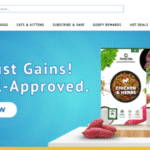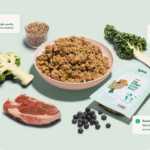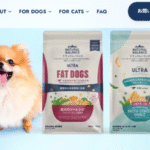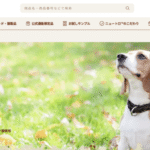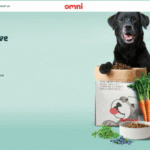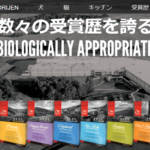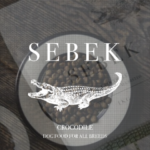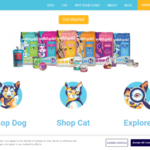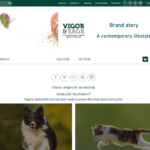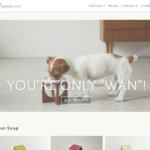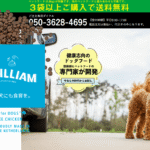目次

このように、お気に入りのソファがボロボロになったり、木製の脚が傷だらけになってしまったり…
愛犬が家具を噛んでしまって悩む飼い主さんは、実はとっても多いんです。
退屈やストレス、歯のムズムズなど、犬が家具を噛むのには必ず原因があり、それを理解することで対策の糸口が見えてきます。
そこで本記事では、
- 犬が家具を噛む原因別の対策
- 犬が家具を噛むときの飼い主のNG対応例
- 家具を噛むのを放置するとどうなる?
などを解説します。
まずは愛犬の行動を確認!家具噛み診断チャート
犬が家具を噛む理由は1つではありません。誤った対策をしてしまうと、かえって噛み癖が悪化することもあります。
そのため、まずは以下の診断チャートで愛犬がなぜ家具を噛むのかを把握しましょう。
| 家具かじり診断チャート | |
|---|---|
| ① | 留守番中に家具を噛むことが多い |
| → YES → A:分離不安 → NO → 次へ |
|
| ② | 散歩や遊びなど、運動量が明らかに足りていない |
| → YES → B:運動不足・退屈 → NO → 次へ |
|
| ③ | 噛んだあとに家具の一部を飲み込んでしまうことがある |
| → YES → C:ストレス・不安 → NO → 次へ |
|
| ④ | 生後6ヶ月未満の子犬である |
| → YES → D:歯の生え変わり → NO → 次へ |
|
| ⑤ | 家具のにおいを嗅いだり、舐めたりしてから噛み始める |
| → YES → E:嗅覚・味覚への感受性 → NO → F:習慣化・クセ |
愛犬が家具を噛む原因は見つけられたでしょうか。
次項では、犬が家具を噛む原因と具体的な対策について一つずつ解説します。
家具を噛む原因【A:分離不安】
犬の気持ちや行動
分離不安とは飼い主と離れることに強い不安や恐怖、ストレスを感じる状態のことで、飼い主さんと一緒にいるときは噛まないのに、留守番中に限って噛む場合は分離不安の可能性が高いでしょう。
とくにひとりでいる時間が多い犬や、過去に飼い主と離れ離れになった経験がある保護犬などに多くみられます。
これは単なるいたずらではなく、「ひとりぼっちで怖い」「早く帰ってきて!」という極度の不安とストレスを解消する手段として、家具やクッション、とくに飼い主のにおいが残ったものを噛むことがあります。
- 飼い主が出かけた直後に家具やドアを噛む
- 留守番中だけ家具がボロボロになる
- 飼い主が帰宅すると過剰に興奮・甘える
- 家具を噛みながら吠える・遠吠えをする
- 留守番前にそわそわ・落ち着きがなくなる
具体的な対策
分離不安は、犬にとって非常に苦しくストレスがかかる状態です。まずは、愛犬の不安な気持ちに寄り添いながら、無理のない範囲で練習を始めてみましょう。
①外出時・帰宅時に構いすぎない
・外出前に声をかけすぎたり、帰宅時に過剰に構ったりしない
→「外出・帰宅=特別なことではない」と学ばせる
・外出前に運動をさせると落ち着いて過ごしやすくなる
②ひとり時間に慣れさせるトレーニング
・別室に移動、数分の外出などから練習する
・犬が落ち着けていられる時間を徐々に延ばす
・離れている間にも安心できるようおもちゃを置く
③安心できる環境を整える
・ハウスやクレートなど、狭くて落ち着ける場所を用意する
・飼い主のにおいがついたタオルやブランケットを置いておく
・ラジオやテレビなどの環境音やリラックス用の音楽も効果的
家具を噛む原因【B:運動不足・退屈】
犬の気持ちや行動
犬は日常生活の中で十分に運動ができていなかったり頭を使う機会が少ないと「何かしたい!」「つまらない!」と感じます。
そのストレスや退屈さ、物足りなさの反動として家具やクッションを噛んでしまうことがあります。
とくにボーダーコリーやジャックラッセルテリアなどの活発な犬種でよくみられる傾向です。
- ウロウロした後に家具を噛み始める
- 散歩が足りていない日ほど噛み癖がひどくなる
- 噛んだあとに興奮して走り回る
- 飼い主の気を引くためにわざと噛む
具体的な対策
運動不足や退屈による家具の噛み癖は、「ダメ」と叱るだけでは改善しません。体力と知的欲求の両方を満たしてあげることで、自然と問題行動が減っていきます。
①毎日の散歩や遊びの見直し
- 散歩はにおい嗅ぎやアップダウンのある道を選ぶと効果的
- ボール投げ、フリスビーなどで走る時間を意識的に作る
- 室内でもロープ遊びなどでエネルギーを発散させる
②頭を使う知育遊びの導入
- おやつ入りおもちゃなどで退屈を防ぐ
- しつけ遊び(おすわり・まて)は精神的な満足に繋がる
③ストレスサインに気づいて早めの対応を
- 家具を噛み始める前にウロウロ・あくび・ため息などのつまらないサインが出ていないかを観察
- サインが見えた時点で軽い遊びや声がけを入れることで噛み癖の予防につながる
家具を噛む原因【C:ストレス・不安】
犬の気持ちや行動
犬は環境や生活リズムの変化、人間関係(飼い主の不在や家族の喧嘩)、音や気温などさまざまな要因からストレスを感じ、家具を噛むことで不安や緊張を解消させようとします。
- 家具を噛む前にウロウロ、あくび、しきりに体を舐める
- 引っ越しなど生活リズムの変化後に噛み行動が増える
- 噛み方が激しく、壊すことが目的のように見える
- 噛んだあとも落ち着かず、興奮している・呼吸が荒い
具体的な対策
ストレスや不安が原因で家具を噛む場合、叱るとかえって逆効果になることが多いです。そのため、外的刺激を減らし、犬の気持ちが安定するような安心できる環境を整えることが最優先です。
①環境の見直し・安心できる居場所の確保
- 静かで落ち着けるハウスやクレートを置く
- 飼い主のにおいがついたブランケットを置く
②日常に安心のルーティンをつくる
- 食事・散歩・遊び・就寝などの時間をある程度固定する
- 「決まった流れがある=安心できる」と犬が感じやすくなる
③飼い主とのポジティブな接触時間を増やす
- スキンシップやブラッシングで「自分は大切にされている」と感じさせる
- 緊張や不安の強い犬にはアイコンタクトだけでも十分な安心材料になることも
④ストレスを発散できる遊び・グッズを活用
- 長時間遊べる知育おもちゃや嗅覚を使うノーズワークは気を紛らわせるのに効果的
- 「家具を噛むよりも楽しい行動」を用意して、噛む以外の選択肢を増やす
家具を噛む原因【D:歯の生え変わり】
犬の気持ちや行動
子犬は生後3〜6か月頃に、乳歯から永久歯への生え変わりが始まります。この時期は歯ぐきにムズムズとした違和感や軽い痛みがあり、それを和らげるために「とにかく何かを噛みたい」状態になります。
この場合、家具を噛むのは不快感の解消行動であり、本能的な反応です。叱ってもやめることは難しく、むしろ「噛みたいのに我慢している」というストレスになってしまうこともあります。
- 家具や布をずっと噛み続ける
- おもちゃより家具の脚などを選ぶ
- 口をしきりに気にして前足でこする
- 食事中にポロッと歯が抜けることがある
具体的な対策
この時期の噛み癖は成長とともに落ち着くことが多いですが、適切な対策がないと習慣化してしまうため注意が必要です。成長の一過程として受け止め、噛んでも良いものを与えましょう。
①噛み心地の良いおもちゃを与える
- 弾力のあるパピー用おもちゃを与える
- 冷やすことで歯ぐきが気持ちよくなるおもちゃ(冷凍ガムなど)を与える
②家具から遠ざける環境作り
- 噛まれたくない家具の周囲をサークルや柵で物理的にブロック
- 家具に苦味スプレーを塗布して、味で避けさせる(誤飲防止にも)
③噛んでいいものを褒めることで習慣化
- おもちゃを噛んだら「いい子だね!」と褒めてごほうび
- 家具に向かう前に、おもちゃへ注意を引き寄せる練習を
家具を噛む原因【E:嗅覚・味覚への感受性】
犬の気持ちや行動
人間の数万倍もの嗅覚を持つ犬は、人間には感じないようなわずかな匂いでも強く反応します。とくにソファやクッション、テーブルの脚などには飼い主の汗や皮脂、食べ物の香りが染み込んでいることが多く、それが「おいしそう」「気になる」という好奇心から噛むことが多くなります。
このタイプの犬はストレス発散や欲求不満ではなく、純粋に匂いに興味を持って噛むという目的であるため、飼い主が叱っても「なぜ怒られたのか理解できない」まま行動が続いてしまいがちです。
- 家具をしつこく嗅いだあとに噛み始める
- 食事中や食後に家具を噛む行動が見られる
- 特定の場所や素材ばかりを集中して噛む
具体的な対策
においに反応するという犬の本能的な行動をやめさせるのではなく、匂いや味を残さない環境づくりや習慣で防ぐことがポイントです。犬にとって「ここは匂わない、味もしない、つまらない」と思わせれば、自然と噛む対象から外れていきます。
①家具や布製品の徹底クリーニング
- 家具やソファはペット用クリーナーで拭き取る
- ブランケットやクッションは定期的に洗濯し、ニオイの蓄積を防ぐ
- 飼い主のにおいが強く残るタオルや服を放置しない
②苦味スプレーやペット用リペレントの活用
- 犬が嫌がる味(苦味・柑橘系)のスプレーを噛まれやすい場所に塗布
- 繰り返し使用することで「ここは噛んでもつまらない」と学習させる
③食事中・食後の行動管理
- 食事後は一時的に別室に移動させる、クレートで落ち着かせるなど、噛みのきっかけから物理的に距離を取らせる
- 食後におもちゃでの遊びやノーズワークを取り入れ、満足感を切り替える
④嗅覚欲求の代替を与える
- 匂いを追う本能的欲求を満たすために、ノーズワークマットやおやつ探し遊びなどを日常に取り入れる
- 嗅覚が満たされると物への執着が自然と弱まることも
家具を噛む原因【F:習慣化・クセ】
犬の気持ちや行動
過去に家具を噛んだことで「楽しかった」「構ってもらえた」「暇つぶしになった」など報酬につながる経験をしていると、飼い主の留守中や目を離したすきに再び同じ行動を繰り返し、癖として定着してしまいます。
これはストレスではなく、ただの習慣や注目を引く手段になっている可能性があります。
- 噛んだ後、飼い主の反応をチラッと見る
- 留守番中に限らず、日常的に噛む
- 噛んでいる時に楽しそう・興奮している
- 何度叱ってもやめない
具体的な対策
習慣化した噛み癖には、「噛んでも得がない」という行動の再学習と、犬にとって満足感のある代替行動を提示することが効果的です。
習慣化した場合は改善に時間がかかりますが、根気強くコツコツと一貫した対応を続けることが大切です。
①無視と切り替えで噛み損にさせる
- 家具を噛んだ瞬間は冷静に無視をする
- 無言でハウスに戻す、場面を切り替える
②噛んでOKなものに興味を移す
- ごほうびが出てくる知育トイやコングに集中させる
- 家具に近づかせないように導線を変える・配置を見直す
③根気よく正しい行動を褒める
- 噛んでいいもの(おもちゃなど)を噛んだらたっぷり褒める
- 毎回ではなく、時々しか褒められない=期待感が高まるで中毒性をつける
犬が家具を噛むときの飼い主のNG対応例
犬が家具を噛んだときに、飼い主さんが「思わずやってしまいがちだけど逆効果になる」NG対応を紹介します。
大きな声で怒鳴る
「ダメなことだと分かってほしい」「びっくりさせればやめるはず」という意図のもと大きな声で「ダメ!」と叱る飼い主さんも多いですが、これはNG対応です。
犬は叱られたことにより飼い主さんに対して「怖い」という感情は覚えても、「家具を噛んだことが悪かった」とは理解できません。逆に強い叱責は不信感や恐怖心を植えつけ、飼い主さんとの関係を悪化させる恐れもあります。
犬を叱るときは、「冷静に、低い声で、短く」がポイントです。噛んでいいおもちゃに切り替え、噛み始めたら褒めてあげましょう。
噛んだあとに構ってしまう
犬が家具を噛んだときに「何してるの?」「またやられた!」と声をかけて注目することもNG対応となります。
犬は「噛めば飼い主が反応してくれる」と学習し、注目を引く手段として噛む行動が強化されることがあります。
犬が家具を噛んでいる瞬間を目撃しても無反応で淡々と対応し、静かに場面を切り替えるのが効果的です。
一貫性のない対応
「あるときは怒る」「別の日は怒らない」「家族間で対応が違う」もNG対応です。
犬は一貫したルールがないと混乱し、「やっていいのか悪いのか分からない」という曖昧なまま習慣化してしまいます。
家族全員で話し合い、毎回同じ対策を統一することが大切です。
家具を噛むのを放置するとどうなる?
犬が家具を噛む行動を「活発な性格だから」「子犬だから仕方ない」「ちょっとだから大丈夫」と放置していると、さまざまな問題に発展する恐れがあります。
まず、家具の破損や修理コストはもちろんですが、最も深刻なのは誤飲による健康被害です。
木片やプラスチック片、布地などを飲み込んでしまうと、胃腸炎や腸閉塞、場合によっては手術が必要になるケースもあります。
さらに、噛むことでストレスを発散したり、飼い主さんの注目を集めると学習すると「噛む=メリットがある行動」として定着してしまいます。これは成犬になってもやめられなくなるリスクを高める要因です。
噛み癖は早期に原因を見極め、適切に対応することが非常に重要です。
まとめ
犬が家具やクッション、ブランケットなどを噛む行動には、必ず理由があります。それは子犬の歯のムズムズだったり、ストレスの発散だったり、飼い主と離れる不安、退屈、においへの反応など犬それぞれ。
「なぜ噛むのか?」という原因を見極め、行動の背景にある気持ちに寄り添った対策をとることが大切です。