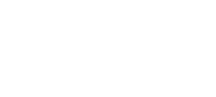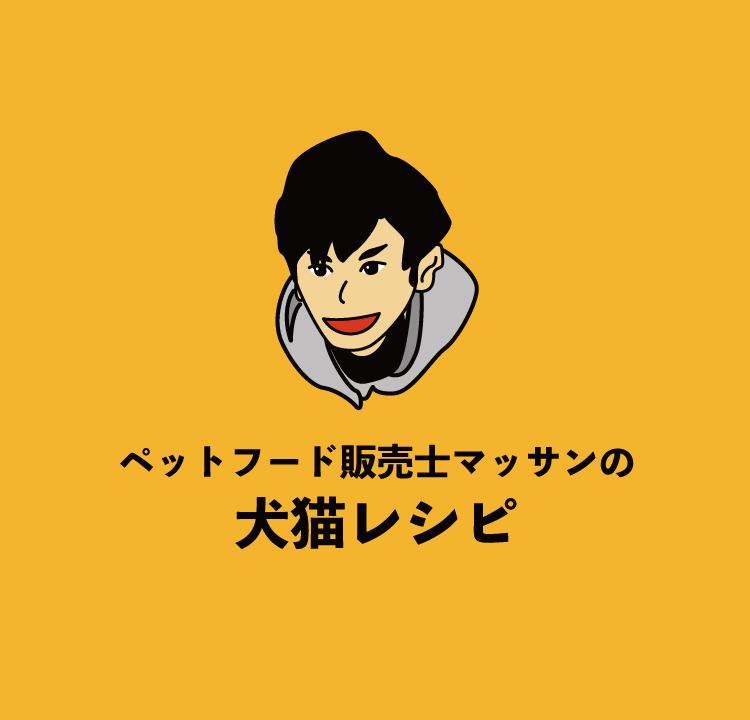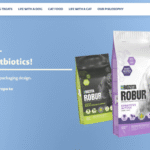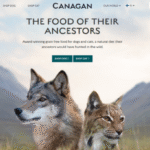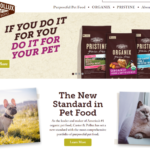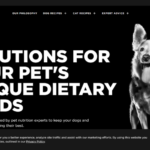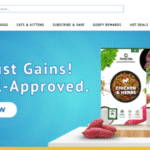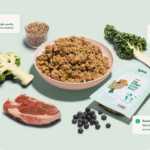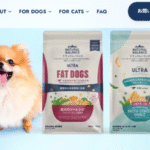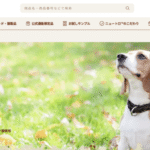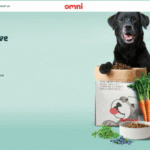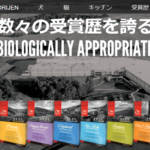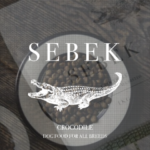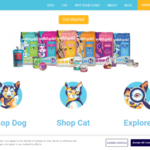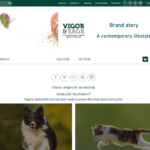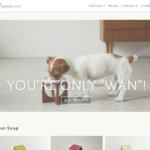目次

そのような場合におすすめなのが「口腔ケアのドッグフード」です。噛むことで歯垢を落とし、歯石や口臭を防ぐ成分も含まれているので、食べながら自然に歯を守れます。

今回は「口腔ケアのドッグフード」の特徴や配合成分、向いている犬について解説します。
口腔ケアのドッグフードとは?
機能性ドッグフードのひとつ
口腔ケアのドッグフードとは、健康維持を目的に特別な栄養設計が施された「機能性ドッグフード」のひとつです。通常の総合栄養食と同じく必要な栄養素を満たしながら、歯垢や歯石の蓄積を抑え、口臭を軽減する働きを持ちます。粒の形や硬さ、配合成分に工夫があり、噛むことで歯を清潔に保つ設計が特徴です。
歯磨きが苦手な犬でも、毎日の食事で自然に歯の健康をサポートでき、口腔トラブルの予防や歯周病対策として注目されています。
さまざまな表記がされる
口腔ケアのドッグフードは、メーカーやブランドによってさまざまな表記がされています。商品パッケージや公式サイトでは、次のような言葉が使われることが多いです。
- オーラルケア
- デンタルケア
- デンタルサポート
- 歯の健康維持
- 口臭ケア
- 歯垢・歯石コントロール
表記や名称は違えど、どれも歯や口腔の健康を維持することを目的としており、内容や目的はさほど差はありません。
口腔ケアを怠ると歯周病に…
犬の口腔ケアを怠ると歯垢が溜まり、やがて石のように固まった「歯石」へと変化します。歯石の表面には細菌が繁殖しやすく、歯茎が赤く腫れる「歯肉炎」や、歯を支える組織が破壊される「歯周病」へと進行します。
歯周病は痛みや口臭だけでなく、歯が抜ける原因にもなり、細菌が血液を通じて全身に広がると、心臓・肝臓・腎臓などの臓器に悪影響を及ぼすこともあります。
毎日の歯磨きや口腔ケアのドッグフードの併用で口腔トラブルを未然に防ぐことが、健康寿命を延ばす第一歩となります。
口腔ケアのドッグフードの特徴
口腔ケアのドッグフードは単に「おいしい」だけでなく、「噛む」「磨く」「清潔に保つ」という3つの要素を組み合わせた構造が特徴で、歯の健康維持と予防を目的としています。
① 食べながら歯垢を落とす粒設計
粒の形や硬さに工夫があり、噛むことで歯の表面に摩擦が生じ、物理的に歯垢を削ぎ落とします。通常のドッグフードよりもやや大きめであることが多く、歯の表面にしっかり接触するよう設計されています。
クロス形状や多面体の粒を採用するブランドも多く、歯の隙間に入り込みやすく、食べながら「歯磨き効果」を得られるのが特徴です。
② 口臭・歯石を防ぐ抗菌成分の配合
歯垢は時間が経つと歯石に変化します。この過程を抑えるために、リン酸塩や亜鉛などのミネラル成分が配合されています。
また、細菌の繁殖を防ぐクロロフィルやハーブ抽出物などが含まれている場合もあり、口臭の原因菌を抑え、口内を清潔に保ちます。
③ 歯茎の健康もサポート
口腔トラブルの多くは歯だけでなく歯茎の炎症から始まります。そこで、抗酸化作用を持つビタミンCやE、免疫を整える成分が配合されることもあります。これらは歯茎の血流や弾力を保ち、歯周病予防にも役立ちます。
口腔ケアのドッグフードに配合される成分と栄養素
リン酸塩(ポリリン酸ナトリウムなど)
リン酸塩は歯石の形成を防ぐ代表的な成分です。歯の表面にミネラルが沈着するのを防ぎ、歯垢が硬化する前にブロックします。歯磨きと併用することで、より効果的な歯石抑制が期待できます。
亜鉛
亜鉛は、口腔内の細菌増殖を抑え、炎症を防ぐ働きを持つミネラルです。亜鉛は皮膚や免疫にも関与しており、口内環境のバランスを整える重要な成分のひとつです。
クロロフィル(葉緑素)
クロロフィルは天然の消臭・抗菌成分として知られ、口臭の原因物質を中和する作用があります。腸内環境を整える働きもあり、内側からの口臭対策にもつながります。
ビタミンC・E
抗酸化作用を持ち、歯茎の血管や組織を守る役割があります。歯周病など炎症性疾患の進行を抑え、歯茎の引き締まりを保つサポートをします。
口腔ケアのドッグフードはどんな犬に向いている?

口腔ケアのドッグフードはすべての犬に役立ちますが、とくに次のような犬におすすめです。
・歯磨きを嫌がる犬
⇒歯ブラシが苦手な犬も毎日の食事でケアできる
・小型犬
⇒歯が密集しているため歯垢が付きやすい
・高齢犬
⇒唾液量が減少し、細菌が繁殖しやすくなるため、口臭が強くなりやすい
・普段ウェットフードを食べている犬
⇒ウェットフードやトッピング中心の犬は歯に摩擦が生じにくく、歯垢が蓄積しやすい
これらの犬たちにとって、口腔ケアフードは「毎日の歯磨き代わり」に近い効果を発揮します。とくに歯周病リスクが高まる7歳以降の犬では、早めの導入が良いでしょう。
口腔ケアドッグフードを選ぶときのポイント
①成分表示を確認する
「歯石予防」や「口臭ケア」と書かれていても、実際にリン酸塩や亜鉛、クロロフィルなどの有効成分が含まれていない製品もあります。パッケージ裏の原材料欄をチェックし、口腔ケアに有効な成分がきちんと含まれているかを確認しましょう。
②粒の大きさ・硬さを犬に合わせる
小型犬に大粒を与えると、噛めずに丸呑みしてしまうことがあります。反対に、大型犬に小粒を与えると摩擦が足りず、十分な効果が得られません。歯のサイズと顎の力に合った粒形状を選ぶことが大切です。
③「総合栄養食」であることを確認
中には「おやつ」や「補助食」として販売されている製品もあります。口腔ケアのドッグフードを主食にする場合は、総合栄養食としてAAFCO基準を満たしているものを選びましょう。
口腔ケアドッグフードの注意点
歯磨きの代わりにはならない
最も重要なのは、「口腔ケアのドッグフード=歯磨き不要」ではないという点です。あくまでサポート的な存在であり、定期的な歯磨きや動物病院でのデンタルケアと併用することで効果を最大限に発揮します。
歯や顎の弱い犬には配慮が必要
高齢犬や歯が欠けている犬には、硬い粒が負担になる場合があります。その場合は、粒をふやかして与えたり、柔らかいタイプの口腔ケアのドッグフードを検討しましょう。
効果を過信しすぎない
一部のドッグフードでは、「歯石除去」と記載されていることがあります。しかし、すでに固着した歯石はドッグフードでは除去できないため、動物病院でのスケーリングが必要となります。
歯石が固着している場合はドッグフードでの改善ではなく、動物病院で相談してみましょう。
まとめ
- 食べながら歯垢を落とす粒形状で、日常的に歯をケアできる
- リン酸塩や亜鉛などの成分が歯石や口臭を抑える効果を持つ
- 小型犬やシニア犬など、歯垢が付きやすい犬に特におすすめ
- 口腔ケアフードは歯磨きの代わりではなく補助的役割と考える
- 獣医の定期チェックと併用し、長く健康な歯を維持することが大切