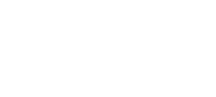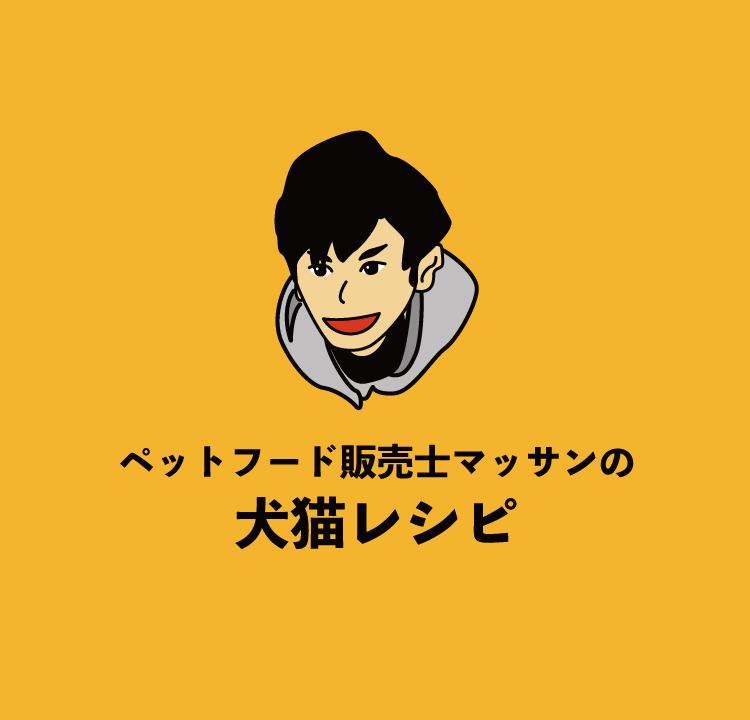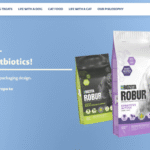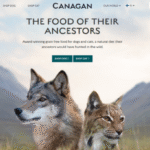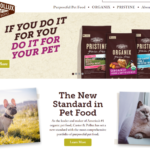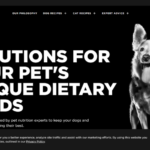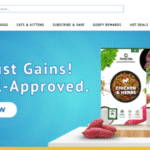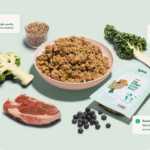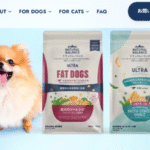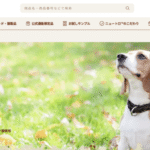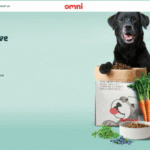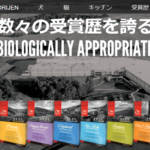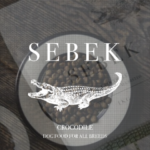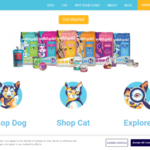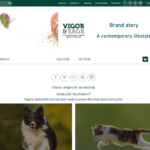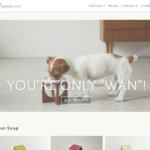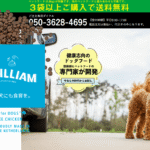目次
梅雨の時期、愛犬がいつもより元気がなかったり、食欲が落ちていたり、外に出たがらなかったりすることはありませんか?
「疲れてるのかな」「眠いのかな」と思って見過ごしてしまいがちですが、実はそれは「梅雨バテ」かもしれません。
犬が梅雨に体調不良になるのはなぜ?

高い湿度と気温は自律神経を乱す
犬は汗腺が足の裏にしかないため、体温調節が苦手です。気温や湿度が高くなると体内に熱がこもりやすくなって自律神経が乱れ、さまざまな症状があらわれます。
梅雨バテはどの犬種・年齢でも起こり得ますが、とくに短頭種(フレンチブルドッグ、パグなど)や大型犬、子犬、高齢犬は蒸し暑さによる不調が顕著に出やすく、注意が必要です。
皮膚トラブルや感染症のリスクが高まる
梅雨は雑菌やカビ、ノミ・ダニが繁殖しやすい季節でもあります。散歩から帰ってきて濡れたまま放置していると皮膚のバリア機能が低下し、外耳炎や膿皮症、湿疹などの皮膚疾患を招きやすくなります。
また、足裏や耳の中は湿気がこもりやすく、清潔に保たなければ感染症の温床になることもあります。
日照不足による活動意欲の低下
雨が続き、日光を浴びる時間が減ることで、セロトニン(幸福ホルモン)やメラトニン(睡眠ホルモン)の分泌が減少する可能性があります。
結果として、元気がない・眠そう・遊びたがらないといった行動変化につながることがあります。
犬に見られる梅雨時の不調のサイン
梅雨の時期に見られやすい体調不良のサインは以下のようなものです。
- 食欲の低下
- 嘔吐・軟便・下痢
- ぐったりしている・寝てばかりいる
- 散歩を嫌がる・動きが鈍い
- 被毛が脂っぽい・皮膚のベタつき
- 呼吸が荒い・軽い熱っぽさ
こうした症状が数日以上続く場合は、単なる梅雨バテで済まされない可能性もあるため、早めに動物病院の受診を検討してください。
食欲の低下や消化不良
高湿度や気圧の変化によって胃腸の働きが鈍くなり、いつも食べているドッグフードを残すことが増えたり、下痢や軟便、嘔吐が見られることがあります。
食事量が減ると体力や免疫力も低下してしまうため、早めの対策が必要です。
寝てばかりで元気がない
日中でも活発に動かず、寝てばかりいるようであれば、身体にだるさを感じている可能性があります。元気がない様子が数日続いたり、呼吸が荒くなるようなら、病院での診察をおすすめします。
皮膚や耳の異常
皮膚に赤みや痒みが出たり、被毛が脂っぽくなる、フケが増える、耳から異臭がするなどは皮膚炎や外耳炎の兆候です。梅雨時は湿度により細菌やカビが繁殖しやすくなるため、発症リスクが高まります。
対策①梅雨を快適に過ごせる生活環境
温度と湿度のコントロールがカギ
犬が快適に感じる温度は20~25℃、湿度は40〜60%が目安です。エアコンの除湿モードや除湿機を使い、湿気をコントロールしましょう。
とくに留守番中はエアコンのタイマー機能などを活用し、温度と湿度を安定させることが重要です。
風通しと清潔さを意識した寝床づくり
犬のベッドやクレートは湿気がこもりやすい素材や分厚い毛布は避け、通気性のよい素材のマットやタオルを敷くようにしましょう。こまめに洗濯・乾燥させることで雑菌の繁殖を防げます。
また、床に直置きするのではなく、通気性のあるスノコやマットを活用することで、湿気のこもりも軽減できます。
対策②食事と水分補給を見直す
食いつきをよくする工夫を取り入れる
梅雨時は食欲が落ちやすい季節です。そんなときは、いつものドッグフードに少し工夫を加えるのがおすすめです。
例えば、鶏の茹で汁や犬用の出汁をドッグフードにかけたり、ウェットフードと混ぜて香りを引き立てることで、嗅覚を刺激して食欲を回復させることができます。
水分をしっかり摂れるよう環境を工夫する
水は1日に数回取り替え、常に清潔な状態を保ちましょう。部屋の複数箇所に水皿を設置したり、循環式給水器を導入することで、自然と飲水量を増やすことができます。ウェットフードやスープ状のおやつを取り入れるのもおすすめです。
対策③皮膚や耳のケアは毎日の習慣に
散歩後のケアが梅雨時はより重要に
雨で濡れたあとの手足やお腹、耳の中はしっかりとタオルで拭き取り、湿気を残さないようにしましょう。とくに肉球の間は乾きにくく、菌が繁殖しやすいため注意が必要です。
必要に応じて、皮膚にやさしいノンアルコールの除菌シートなどを活用するのもよいでしょう。
皮膚トラブルがある場合は早めに受診を
皮膚にかさぶたや赤みが出ている、強く痒がるなどの症状が見られたら、自己判断で市販薬を使わず、必ず獣医師の診察を受けましょう。膿皮症やマラセチア感染などは放置すると悪化しやすく、長期的な治療が必要になることもあります。
対策④運動不足・ストレスの対策も忘れずに
室内遊びでストレス発散を
雨の日が続くと散歩の回数が減り、運動不足からストレスが溜まりやすくなります。お気に入りのおもちゃを使った引っ張りっこや、知育トイでの遊びなど、室内でも楽しめる遊びの時間を意識して作りましょう。飼い主との触れ合いも、犬にとっては大きなストレス軽減になります。
雨でもできる工夫したお散歩を
どうしても散歩が必要な犬種や、トイレが外派の犬は、短時間でも雨の合間を縫って外に出るようにしましょう。撥水性のあるレインコートや足を守るブーツを使えば、濡れることへの負担も軽減できます。帰宅後はしっかり乾かすことを忘れずに。
まとめ
梅雨は犬にとって心身ともに負担のかかる季節です。蒸し暑さや湿気による体調不良、運動不足によるストレスなど、見逃せない要因がたくさんあります。しかし、環境を整え、食事やケアを少し工夫することで、犬はこの時期も快適に過ごすことができます。
大切なのは「ちょっとした異変に気づく目」と「すぐに対処できる準備」。愛犬が元気に梅雨を乗り切れるよう、日々の観察と対応を心がけましょう。