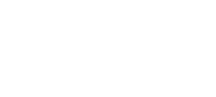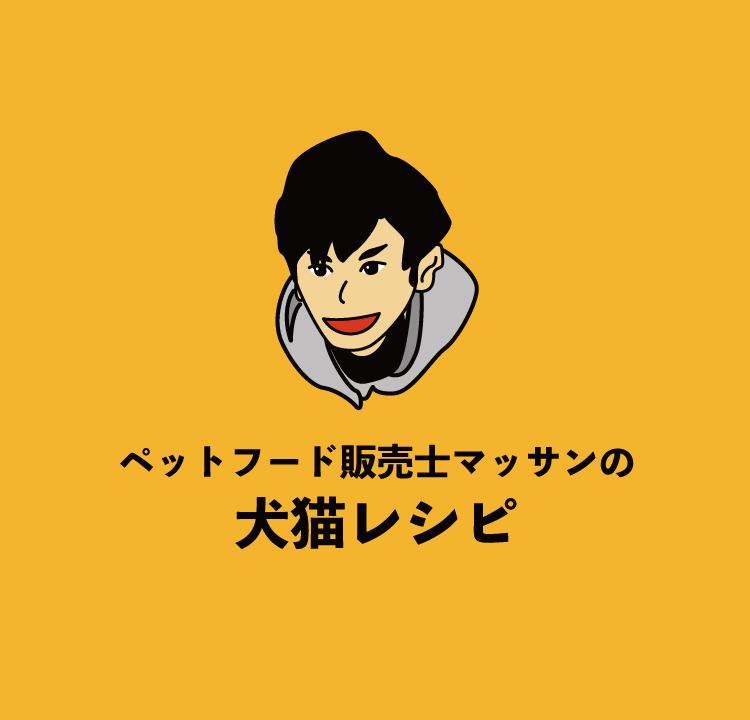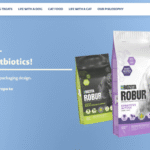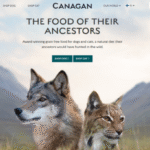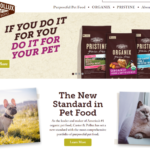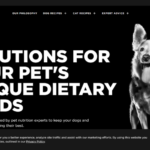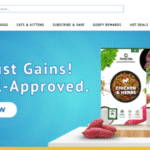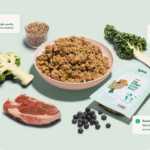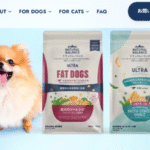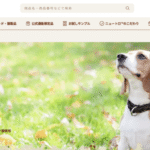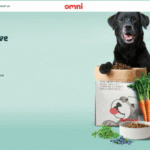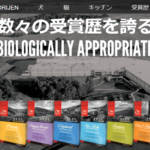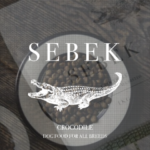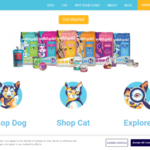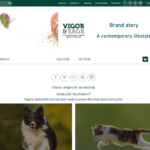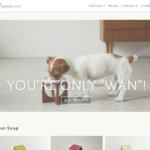HACCPとは
HACCP(ハサップ)とは、「Hazard Analysis and Critical Control Point(危害要因分析・重要管理点)」の略語です。もともとはNASAの宇宙食開発において、食の安全を確保するために誕生した概念で、現在では世界各国の食品工場やペットフード工場に採用されています。
HACCPの特徴は、「問題が起きてから対応する」のではなく、「問題が起きないように製造工程そのものを管理する」という点にあります。
原材料の受け入れから製造、包装、出荷まですべての工程を分析し、「どこでどんなリスクがあるか」を洗い出し、「ここで確実にチェックすれば安全が守れる」というポイントを定めて管理していきます。人間と同じように犬の健康にも大きな影響を与える危害要因を未然に防ぐことがHACCPの目的です。
HACCP対応のドッグフードの安全性
感覚や経験ではなく、数値化して安全を保つ
HACCP対応のドッグフードは、製造過程におけるリスク管理が科学的に行われている点が最大の特徴です。
例えば、サルモネラ菌の増殖や異物の混入といった危害要因に対して、どの工程で発生し得るのかを事前に分析し、問題が起きやすい箇所を「重要管理点」として設定します。その上で、温度管理・殺菌処理・異物検出などを徹底し、常に一定の品質を保つように設計されています。
こうした管理体制は、単なる感覚や経験に頼るものではなく、数値に基づいた検証が可能であるため、安定した品質で製品を供給できるという大きな利点があり、それが飼い主にとっての安心材料となります。
「見えないリスク」を可視化し、未然に防ぐ仕組み
ドッグフードの安全性では原材料や成分ばかりに注目されがちですが、実際には製造工程に潜むリスクこそが見落とされやすいポイントです。HACCPはこの「見えない危険」に対して光を当て、発生前に食い止めるための予防的なシステムです。
例えば、原材料の搬入段階ですでに微生物汚染がある可能性を検討し、サンプル検査や一定時間内の処理ルールを設けるなど、細部にわたる安全管理が組み込まれています。
このように、HACCPに対応したドッグフードは、飼い主の目に見えない製造現場での衛生管理を徹底することで高い安全性を実現しているのです。
HACCP対応に関するよくある誤解
HACCP未対応のドッグフードは危険?

HACCPはあくまで安全管理の手法であり、HACCP未対応だからといって危険なドッグフードとは言えません。
重要なのは「リスクに対してどれだけ事前に備えているか」です。製造現場においてHACCPのような管理が行われていない場合、万が一のときのトラブル発生率が高くなる可能性は否めません。
とくに海外製品や個人輸入のドッグフードなどでは、HACCPへの対応状況が不明なまま販売されていることもあり、こうした場合には慎重な判断が求められます。愛犬の体調やアレルギー体質などを踏まえた上で、信頼できるメーカーの情報を丁寧に確認することが重要です。
HACCP対応=高品質?

HACCPはあくまで「衛生管理」や「工程管理」の枠組みであり、使用される原材料のランクや栄養バランス、添加物の有無といった“品質の良し悪し”とは直接関係がありません。
つまり、HACCPに対応していても「鶏副産物ミールや香料が多用されている」ような商品も存在しますし、逆にHACCP認証を受けていなくても、原材料に徹底的にこだわった小規模メーカーも存在します。
HACCPは「安全性の土台」であって「品質の評価基準」ではないため、安全性と品質の両方を見極めることが重要となります。
「GMP」や「ISO」との違い
HACCPと並んでよく登場するのが、「GMP」や「ISO」といった衛生管理や品質管理に関する用語です。これらは似ているようで異なる意味を持っています。
- HACCP:現場の工程に密着した実践的な管理手法
- GMPやISO:HACCPの上に乗る全体的な運用ルール
と捉えると理解しやすいでしょう。
まとめ
- HACCPは製造工程のリスクを事前に管理する国際的な衛生手法
- 対応フードは異物混入や細菌汚染のリスクを抑えている
- 未対応だから危険とは限らないが、安全管理体制に差が出る
- HACCP対応でも原材料の質や栄養価は別に見極めが必要
- GMPやISOとは目的が異なり、HACCPは工程管理に特化している