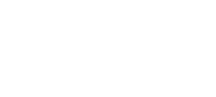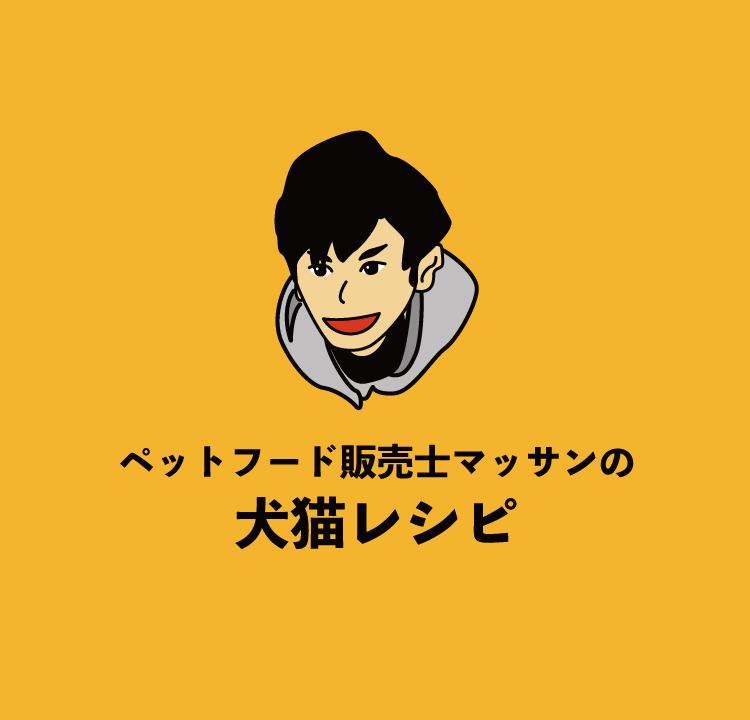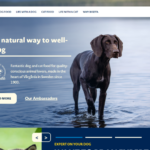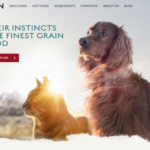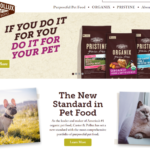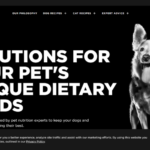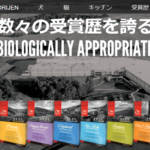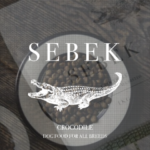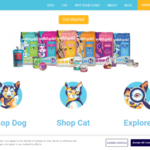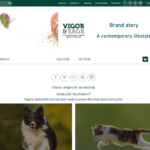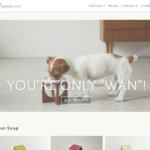目次
犬の瞳に左右で異なる色を持つ「オッドアイ」を見つけたとき、その神秘的な印象に思わず目を奪われる人も多いでしょう。オッドアイは猫に多い印象がありますが、犬でも見られる現象です。
この記事では、犬の目の色が左右で違う理由や、オッドアイになりやすい犬種、視力や健康への影響、オッドアイの犬の価格、そして注意したい病気の可能性について解説します。
オッドアイとは?左右で目の色が異なる現象
オッドアイ(odd eye)とは、片方の目が青く、もう片方が茶色など異なる色をしている状態を指します。正式には「虹彩異色症(heterochromia iridum)」と呼ばれる遺伝的あるいは後天的な要因による変異で、人間を含むさまざまな哺乳類で観察されています。犬では先天的な遺伝子の働きによって発現することが多く、外見の美しさから特別視されることもあります。
犬のオッドアイは、メラニン色素の分布に偏りがあることで生じます。青い目の方にはメラニンが少なく、茶色い目の方には多く含まれている状態です。この色素の分布の違いによって、まったく異なる瞳の色が生まれるのです。
オッドアイになりやすい犬種
オッドアイはすべての犬に見られるわけではなく、特定の犬種で高い確率で発現します。とくに被毛が白っぽく、メラニン量が少なめの犬種や、特定の遺伝子(とくに「白斑遺伝子」や「マール遺伝子」)をもつ犬種に多く見られます。
代表的な犬種には下記のような例があります。
・シベリアン・ハスキー
→オッドアイの犬種として最もよく知られています。白地に黒やグレーの毛色、鋭い顔立ち、そして左右で違う目の色という外見的特徴が人気で、オッドアイでも視力に問題がないケースが多いとされます。
・オーストラリアン・シェパード
→「マール遺伝子」の影響を受けやすい犬種です。毛色と同様に、虹彩の色も不均一になりやすく、オッドアイや部分的な虹彩異色症(片目の中で色が分かれる)も見られます。
・ボーダー・コリー
→一部にマールカラーが認められ、オッドアイになることもあります。ただし発現率はやや低めです。
・ダルメシアン
→白と黒のまだら模様が印象的な犬種ですが、稀にオッドアイが発現することがあります。遺伝的に聴覚異常を併発する可能性があるため、注意が必要です。
「白斑遺伝子」と「マール遺伝子」について
白斑遺伝子(ホワイトスポッティング遺伝子)とは、犬の体毛に白い模様(斑)を生じさせる遺伝子です。正式には「S遺伝子(Spotting gene)」と呼ばれ、白い毛色の範囲を決める役割を担っており、白斑の出方には個体差があります。この遺伝子の影響で、色素を持たない白毛が目の周辺や耳の内側にも現れると、メラニン不足により視覚や聴覚に障害が出る可能性があります。とくに青い目と白毛が組み合わさる場合、先天性難聴との関連が報告されており、健康リスクに注意が必要です。
マール遺伝子(Merle遺伝子)とは、犬の毛色に大理石のような斑模様を生じさせる遺伝子で、被毛の色を不均一に薄める働きをします。この遺伝子を1つだけ持つ「ヘテロ接合型(Mm)」では美しい模様やオッドアイが現れやすくなりますが、両親からマール遺伝子を1つずつ受け継いだ「ホモ接合型(MM)」では、視覚・聴覚障害や発育不全などの先天的な異常を抱えるリスクが高まります。そのため、マール同士の交配は避けるべきとされ、繁殖には慎重な判断が求められます。
オッドアイは視力に影響がある?
視力に影響はない。ただし、両親がマール遺伝子の場合は注意
オッドアイの犬を見て「視力に問題があるのでは?」と心配される方もいるかもしれませんが、結論からいえば、先天的なオッドアイの多くは視力に影響を与えません。片方の目が青いからといって、その目が見えていないというわけではなく、通常通りの視覚能力を保っている場合が大半です。
ただし例外もあり、「白毛遺伝子」と「オッドアイ」、「聴覚障害」がセットで発現するケースもあります。とくに両親がともにマール遺伝子を持っている場合、生まれてくる子犬が視覚や聴覚に障害を持つ確率が高くなるため、繁殖には十分な配慮が必要です。
オッドアイや白毛の犬に見られる先天性難聴のリスク
この研究は、ダルメシアンやブル・テリアなど、先天的な色素異常がある犬種における難聴の発生率を調べたものです。
脳の反応を測る検査を通じて聴力を確認した結果、最も難聴の割合が高かったのはダルメシアン、最も低かったのはイングリッシュ・コッカー・スパニエルでした。性別による差は見られませんでしたが、ダルメシアンでは青い目の犬が難聴になりやすく、体に斑点が多い犬は比較的耳が聞こえやすい傾向がありました。また、ブル・テリアでは白い毛色の個体の方が有色の個体よりも聴覚障害のリスクが高く、親犬が難聴である場合は子犬も難聴になる可能性が高まることが示されています。
見た目の特徴と聴力には関連性があるため、オッドアイや白毛の犬を迎える際には、聴力検査を行い健康状態をしっかり確認することが大切です。
参考:Deafness prevalence and pigmentation and gender associations in dog breeds at risk
オッドアイの犬の価格は高くなる?
オッドアイの犬はその神秘的な見た目から「希少価値がある」「高額になるのでは?」と思われがちですが、必ずしも価格が上がるとは限りません。ブリーダーやペットショップの方針、個体の健康状態、血統、犬種の需要などが影響するため、一概にオッドアイだから高い・安いとは言い切れないのが実情です。
例えばシベリアン・ハスキーでは、オッドアイは特別視されることもありますが、一般的な価格帯から大きく外れることは少なく、20万〜40万円程度で販売されていることが多いです。ただし、オッドアイかつ良血統でショードッグ向けとなると、価格が跳ね上がることもあります。
一方、オーストラリアン・シェパードのように、オッドアイがマール遺伝子によるものだと、繁殖時のリスクを避けるために敬遠されることもあるため、むしろ価格が抑えられるケースもあります。
オッドアイの犬に起こり得る病気や注意点
オッドアイ自体は病気ではありませんが、遺伝子の組み合わせによって視覚・聴覚異常や他の先天性疾患が併発するリスクが存在します。とくに注意が必要なのは下記のようなケースです。
聴覚障害(先天性難聴)
白毛・青い目・オッドアイの組み合わせを持つ犬には、先天的な聴覚障害が見られることがあります。とくに片耳または両耳が聞こえない「感音性難聴」は、ダルメシアンやマールカラーを持つ犬種に多い傾向があります。
視覚障害・眼の異常
オッドアイの青い目の方において、稀に虹彩形成不全や小眼球症、視神経異常などが起こる場合があります。視覚に問題があるかどうかは、子犬期からの行動観察や動物病院での検査で判断できます。
光に対する感受性(まぶしがり)
青い目の犬は、虹彩にメラニンが少ないため、太陽光や強いライトに対してまぶしがる傾向があるとされています。外出時にはサングラスのようなアイウェアを着用する犬もいます。
オッドアイの犬との暮らし:美しさの裏にある責任
オッドアイの犬と暮らすことは、見た目の美しさや話題性だけでなく、その子に合った適切なケアや理解も必要とされます。とくに視覚・聴覚に不安のある場合、日常生活やしつけの方法に配慮が必要です。
聴覚に障害がある犬の場合は、声による指示ではなくハンドサインによるトレーニングが有効です。また、周囲の物音に気づけないことで驚きやすくなるため、散歩中や他の犬と接するときにも慎重な対応が求められます。
見た目の魅力に惹かれてオッドアイの犬を選ぶことは自然なことですが、その美しさの背景にある遺伝や身体の状態についても理解した上で迎えることが、飼い主としての責任といえるでしょう。
まとめ
- オッドアイとは片方の目が青く、もう片方が異なる色をしている状態のこと
- オッドアイは先天的な遺伝子の働きによって発現する
- オッドアイはハスキーやオーストラリアン・シェパードによくみられる
- オッドアイは視力に影響はないが、両親がマール遺伝子の場合は注意が必要