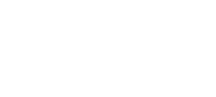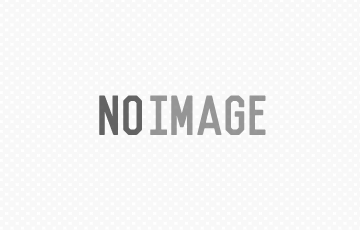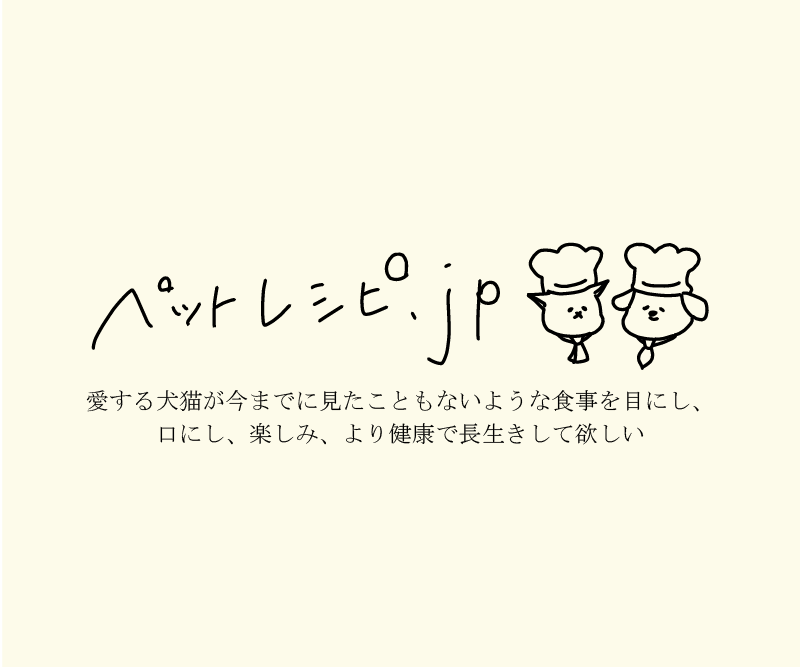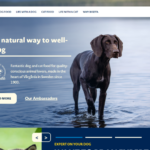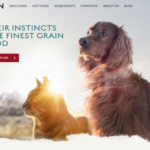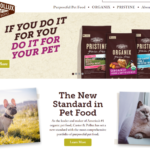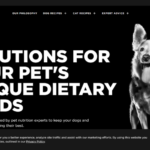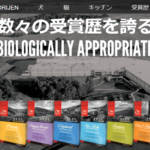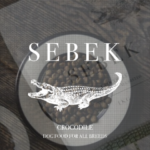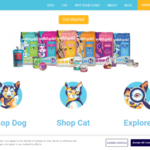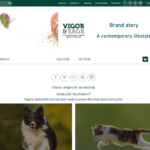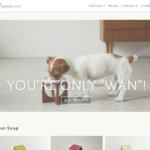「おもちゃ買ったのに全然遊んでくれない…」
「遊ばせたほうが運動になるし、健康に良いと思っていたのに」
「楽しくないのかな?ストレスがたまってないか不安」
犬にとっておもちゃは大切な刺激のひとつ。愛犬がおもちゃに興味がなくて、不安になっている飼い主さんも多いのではないでしょうか。
しかし、すべての犬が自然とおもちゃに興味を持つわけではありません。個々の性格や過去の経験、年齢などによってはおもちゃへの関心が薄い・興味がない犬もいます。
この記事では、
- 犬がおもちゃに興味がないのはなぜなのか
- 興味がないけど遊ばせるべきなのか
- 犬の性格に合わせた無理のない向き合い方
について解説していきます。
おもちゃに興味がない犬のよくある行動
おもちゃに興味がない犬は、おもちゃを目の前にしても反応が薄い、あるいはまったく関心がないといった行動をとります。
下記はおもちゃに興味がない犬によく見られる行動の具体例です。
- おもちゃを見ない、触れようとしない
- おもちゃの匂いを嗅ぐだけで、すぐに立ち去る
- おもちゃを投げても無視する、取りに行かない
- おもちゃよりも他のこと(飼い主、外の音など)に注意が移る
- おもちゃを見ても、ベッドで寝たりくつろぎ続ける
- おもちゃに近づくのを避ける、距離をとる
犬がおもちゃに興味がないのはなぜ?

犬がおもちゃに興味がないのは、下記の6点が考えられます。
- 性格・犬種による傾向
- おもちゃの遊び方が分からない
- おもちゃ以外の遊びが好き
- 飼い主との関係
- 年齢や成長による変化
- ストレス・病気・体調不良の可能性
①性格・犬種による傾向
犬にはそれぞれ個性があり、活発で遊び好きな子もいれば、おっとりしていておもちゃよりも落ち着いた過ごし方を好む子もいます。
また、犬種によっても遊びへの関心に差があります。
例えばラブラドール・レトリバーのような作業欲求が強い犬は遊びが大好きな傾向がありますが、柴犬のように独立心の強い犬は自分のペースで過ごすことを好むため、おもちゃにあまり執着しないこともあります。
②おもちゃの遊び方が分からない
犬がおもちゃに興味がない理由に、「遊び方が分からない」というケースがあります。
特に子犬期にあまり遊びの経験がなかった犬や、人との関わりが少なかった元保護犬などによく見られます。目の前におもちゃがあっても、「これをどうすればいいのか分からない」「噛んでいいものか迷っている」と戸惑ってしまうことがあります。
そんなときは飼い主が実際におもちゃを動かして見せたり、一緒に遊んであげることが大切です。おやつを使ったり褒めながら一緒に遊ぶことで、犬は徐々におもちゃに興味を示していきます。
③おもちゃ以外の遊びが好き
犬によっては、おもちゃで遊ぶよりも他の遊びの方が好きという場合があります。
例えば散歩中ににおいを嗅ぐのが大好きな犬や、走り回ることに夢中な犬もいます。中には、飼い主のそばでまったり過ごすだけで満足している子もいるでしょう。
これは、おもちゃに興味がないということではなく、おもちゃよりも他に楽しいことがあるということです。
人間に例えると、ゲームに興味がない人のようなものです。例えば、ある人はゲームが大好きで何時間も熱中しますが、ある人は読書や散歩の方が楽しいと感じるでしょう。
どちらが正しい・間違っているということではなく、「楽しみ方の違い」なんです。
犬が何に喜びを感じるのかをよく観察し、その子の「楽しい」を理解してあげることが、良い関係を築くポイントです。
④飼い主さんが大好き
犬がおもちゃに興味がない理由のひとつとして、「飼い主さんのことが大好きすぎるから」というケースもあります。
飼い主さんに常にベッタリな犬は人との関わりを最優先するため、おもちゃや遊びへのモチベーションが湧きづらいことも。
もちろん、犬が飼い主さんのことが大好きなのは良いことなのですが、飼い主さんの姿が見えないと極端に落ち着かなくなったり、吠えるなどの行動が増える場合は分離不安の可能性があります。
「おもちゃも楽しい」と感じさせて精神的な自立や一人遊びを習慣づけることは、QOL(生活の質)を高めることにつながります。
⑤年齢や成長による変化
犬は年齢とともに遊び方や関心が変化していきます。
子犬の頃はエネルギーが有り余っていておもちゃにも強い関心を示しますが、成犬になるにつれて落ち着き、おもちゃ遊びへの興味が自然と薄れることもあります。
特にシニア期に入ると体力や好奇心が減退し、静かに過ごすことを好むようになる犬も多いです。また、加齢により視力や聴力が低下した場合、おもちゃの音や動きへの反応も鈍くなることもあります。
こうした変化は自然な老化の一部なので、「前は遊んだのに…」と不安になる必要はありません。その時々の愛犬のペースに寄り添いながら、無理なく過ごせる環境を整えてあげることが大切です。
⑥ストレス・体調不良・病気の可能性
つい最近までおもちゃで遊んでいたのに急におもちゃに興味がなくなった場合は、ストレスや体調不良、病気が原因かもしれません。
例えば、環境の変化や生活リズムの乱れ、騒音、飼い主さんとの関係の不安などがストレスとなり、遊ぶ気力を奪ってしまうことがあります。
また関節や歯の痛み、内臓の不調などがあると、身体的につらくて遊ぶどころではなくなります。
元気や食欲の有無も併せて確認し、少しでも様子がおかしいと感じたら早めに動物病院を受診しましょう。
「遊ばせなきゃ」のプレッシャーはいりません

犬の個性や好みに合わせた遊びを選ぶことが大切
おもちゃで遊ばない、興味がない愛犬を見ると「遊ばせた方がいいのかな」と不安になるかと思いますが、おもちゃに興味がないのであれば無理に遊ばせる必要はありません。
犬によって好む刺激はさまざまで、おもちゃで遊ぶより外を歩くのが好きな子、飼い主との触れ合いが好きな子、においを嗅ぐのに夢中な子、ゴロゴロするのが幸せに感じる子もいます。
大切なのは、飼い主さんが「遊び方は一つじゃない」と理解し、犬の個性や好みに合わせた関わり方を選ぶことです。
ただし、健康維持や認知的な刺激には「遊び」は非常に重要
ただし、心身の健康維持や認知的な刺激の観点からは「遊び」は非常に重要です。
おもちゃに興味がないからと言っておもちゃ遊びをしなくていいというわけではなく、散歩やにおい嗅ぎ、トレーニングゲームなどを取り入れることで同じような効果を得ることができます。
特ににおい嗅ぎは犬にとって本能を満たす行動であり、脳を活性化させる「嗅覚の知育」ともいえる活動です。また、簡単なコマンドを使ったトリック遊びや、フードを使った探しものゲームなども、犬の集中力や判断力を育てる良い刺激になります。
重要なのは、「遊び=おもちゃ」だけにこだわらず、犬が前向きな気持ちで取り組める活動を日常の中に取り入れていくことです。
この子は無理に遊ばせなくてもOK
一方で、無理におもちゃに興味を持たせなくてもいい犬もいます。
- 持病や関節痛などで運動が難しい犬
- 他の刺激(人との触れ合いや散歩など)で満たされている犬
- おもちゃに強い不安や恐怖反応を示す犬
これらの特徴を持つ犬は、無理に遊ばせようとすると逆にストレスになることがあります。
①持病や関節痛などで運動が難しい犬
おもちゃに興味はあっても、加齢や持病、関節痛などで運動が難しい犬には無理に遊ばせる必要はありません。無理な動きは痛みやストレスの原因になるため、体に負担の少ない遊び方を工夫することが大切です。
例えば、寝たままできる知育トイやノーズワークマットを使えば、頭を使いながら楽しむことができます。
犬の体調や年齢に合わせて、無理なく遊べる方法を選ぶことが心身のケアにつながります。
②他の刺激で満たされている犬
他の刺激で十分に満たされている犬に対しては、無理におもちゃで遊ばせる必要はありません。
飼い主さんとの触れ合いや散歩、においを嗅ぐことなど、他の刺激で満足していればそれがその子にとっての理想的な過ごし方です。
③おもちゃに不安や恐怖がある犬
音や動きに敏感に反応したり、社会化期に十分な刺激を受けていなかったり、過去の嫌な経験などにより、おもちゃに対して不安や恐怖を持っていることもあります。
こうした犬には無理におもちゃで遊ばせず、ノーズワーク(におい探し遊び)をしたり、初めての道を歩いたり、ゆっくり撫でたりマッサージするなど、おもちゃ以外の遊びやスキンシップがおすすめです。
まとめ
愛犬がおもちゃに興味がないからといって心配しすぎる必要はありません。
大事なのは、犬の個性を尊重しながら、無理のない範囲で楽しく関われる方法を見つけていくことです。おもちゃにこだわりすぎず、犬と飼い主が一緒に心地よい時間を過ごせる形を探していきましょう。